しつ問1:建ちく士って、どんな仕事ですか? (1年/宮城県/うさこ)
 |
| せっ計図通りのすん法(すんぽう)かな? とメジャーではかる大津さん。 |
お答え1:建ちく士は、おせ主さん(家を注文した人)の希望(きぼう)する建物(たてもの)をつくる仕事です。
「こんなキッチンにしたい」「日当たりのよい広い部屋があったらいいな」というリクエストを聞きながら、せっ計図をつくります。
また新しい家を建(た)てるだけではなく、「地しんがきたときのことを考えて、家をじょう夫(じょうぶ)にしたい」「おふろを新しくしたい」といったように、家の一部を直したり、新しくしたりする注文を受けることもあります。
せっ計図ができあがったら、建ちくげん場で、図面通りに作業が進んでいるかをチェックします。
しつ問2:どんな人といっしょに家をつくるの?(3年/静岡県/明日は晴れ!)
お答え2:家づくりには、大工(だいく)さんはもちろん、電気屋さん、かべ紙やじゅうたんをはったりする内そう屋さん、屋根にかわらをしく屋根屋さんなど、たくさんの人が参加(さんか)します。建ちく士は、みんなをまとめるのも大切な仕事です。
建ちく士は、仕事が計画的(けいかくてき)に進むよう、全員の仕事に気を配ります。ちょうど交通整理をするけい察官(けいさつかん)や、オーケストラをまとめる指き者のようなそんざいです。げん場かんとくをするときは、「大工(だいく)さんは明日(あす)までにこの土台を完成(かんせい)させてください」「しばらく雨が続(つづ)きそうだから、今日中(きょうじゅう)にがんばって仕上げてしまいましょう」など、よりよいはんだんをする力が求(もと)められます。
しつ問3:家のせっ計ってどうやって考えるの?(4年/愛知県/ハッピィ)
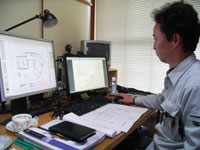 パソコンを使ってせっ計図をかくんだよ。 パソコンを使ってせっ計図をかくんだよ。 |
お答え3:まず、建(た)てる場所の気候(きこう)、家族の人数、それぞれの年れいなどを調べます。そして、住む人の意見を取り入れた家を考えます。たとえば、「家族がいっぱいおしゃべりできる家にしたい」という希望(きぼう)をかなえるにはどんな家がよいでしょう。それぞれの部屋は少し小さくても、そのぶん広いリビングをつくれば、みんなが集まって、ゆっくりすごすことができます。また、キッチンからダイニング(食事をする部屋)を見わたせるようにすれば、家族とおしゃべりしながら料理(りょうり)をすることができますね。
また、家は何十年も住み続(つづ)けるものです。住む人が年をとったとき、子どもが家を出ていったときなど、家族の変化(へんか)を想ぞうしながら、せっ計することも大切です。
しつ問4:なぜ建ちく士になりたいと思ったの? (2年/長崎県/ぴょん)
 いろんな人が働(はたら)いている建(けん)ちくげん場。 いろんな人が働(はたら)いている建(けん)ちくげん場。 |
お答え4:20才くらいのころに、建(けん)ちくげん場でアルバイトをしたことがきっかけです。「ここからここまで、白いペンキでぬってください」「スギの木を使って、2.5メートルのすん法(すんぽう)でお願(ねが)いします」など、てきぱきと指じを出している人がいて、「わあ、かっこいいなあ」とあこがれたのがきっかけです。この人が建ちく士であることを知り、ぼくもなりたい!と思うようになりました。
そして、家を建(た)てるには、たくさんの人の力が必要(ひつよう)です。小さいころから野球をやっていて、チームプレーが大すきだったぼくにはぴったりの仕事だなと思っています。
しつ問5:きけんな目にあうことってある?(5年/愛知県/建築士だーいす気君)
 ヘルメットをかぶってきけんから身を守るんだって。 ヘルメットをかぶってきけんから身を守るんだって。 |
お答え5:建(けん)ちくげん場にいると、上から木や道具が落ちてきたり、足場(鉄などでつくる足をかける場所。
高いところで工事をするときに使う)から落ちることもあります。屋根からストンと落ちたこともありますよ。落ちた場所がやわらかかったのでケガをしないですみましたが、本当にびっくりしました。げん場にいるときヘルメットは欠(か)かせません!
しつ問6:むずかしいことは何ですか?(4年/福島県/あきぽ)
  |
| 「せっ計図だけではわかりづらいので、も型(もけい)をつくっておせ主さんに具体的(ぐたいてき)なイメージを持ってもらいます」と大津さん。 |
お答え6:多くのおせ主(家を注文した人)さんにとって、家を建(た)てるのは初(はじ)めてのけいけんです。そのため、家がどういうふうにできるのか、どんな材料(ざいりょう)が使われているのか、知っている人はほとんどいません。
おせ主さんの言いなりになっても、よい家になるとはかぎらないのです。
また、たくさんの希望(きぼう)があっても、予算や材料の問題などで、実げんできないこともあります。住む人に満足(まんぞく)してもらえる家であり、安全で住みやすい家をつくるのは、とてもむずかしいことですね。
しつ問7:うれしいことは何ですか?(4年/沖縄県/みっちゃん)
お答え7:家が完成(かんせい)したあと、人が住み、生活がはじまると、家の歴史(れきし)がいよいよスタートしたなと思います。夜、家に明かりがついているのを見ると「みんな、ここでくらしているんだな」と、とてもうれしくなります。
ぼくがせっ計した家に住む人から「赤ちゃんが生まれて、新しい家族がふえました」「今年(ことし)は庭にきれいなお花を植えました」など、楽しくくらしている様子を知らせる手紙をもらうのもうれしいですね。
しつ問8:自分の家を建(た)てるなら、どんな家にする?(2年/岐阜県/たける)
 |
| 大津さんがせっ計した家。木をたくさん使った気持ちのよい家だよ。 |
お答え8:スギやヒノキなど、日本の木を使った家を建(た)てたいですね。日本の木は安くて、じょうぶで、加工(かこう)しやすいなど、よい点がたくさんあります。それに、とてもよいかおりがします。
広々とした部屋より、せまい部屋にいるほうが落ち着くので、本を読んだり、のんびりできる小さい部屋があったらいいなあ。それからせっ計は、だれかにたのみたいですね。あれこれわがままを言いたいので(笑)。
しつ問9:どんなせっ計が得意(とくい)ですか?(6年/石川県/たんぽぽ)
お答え9:その土地の気候(きこう)に合わせた家を考えるのが得意です。寒い土地では、あたたかくすごせるような、しっ気が多い土地では風通しがよくなるようなせっ計を心がけます。
また家の中では、キッチンを考えるのがすきです。ぼくが食いしんぼうだからかもしれません。「どんな料理(りょうり)をしますか?」「おなべはどのくらい持っていますか?」「調味料を置(お)く場所がほしいですか?」など、いろんなことを聞きながら、使いやすいキッチンになるようにせっ計します。
しつ問10:わたしの家では、家を建(た)てるとき「地ちん祭」というのを行いました。家を建てるときの、ぎ式について教えてください。(6年/愛知県/きよら)
 |
| 地ちん祭の様子。 |
お答え10:「地ちん祭」というのは、家を建(た)てる前に、工事が無事(ぶじ)に進むよう、その土地の神様においのりするものです。
また、屋根の一番高い場所に「むな木」をわたすことを「むね上げ」といい、そのときには「上とう式」を行います。おせ主さん(家を注文した人)が、しょく人さんにごはんやお酒をふるまい、しょく人さんはお礼におめでたい歌を歌ったりします。屋根にまよけの「や」をかざったり、家の四すみに塩(しお)、水、米をまいたりもしますよ。
また、むな木には、むな札(ふだ)といって、そのときの日づけ、家族の名前などを書いてはります。古い家をこわすと、むな札が見つかることがあります。ちょうどタイムカプセルのようなものですね。
|

